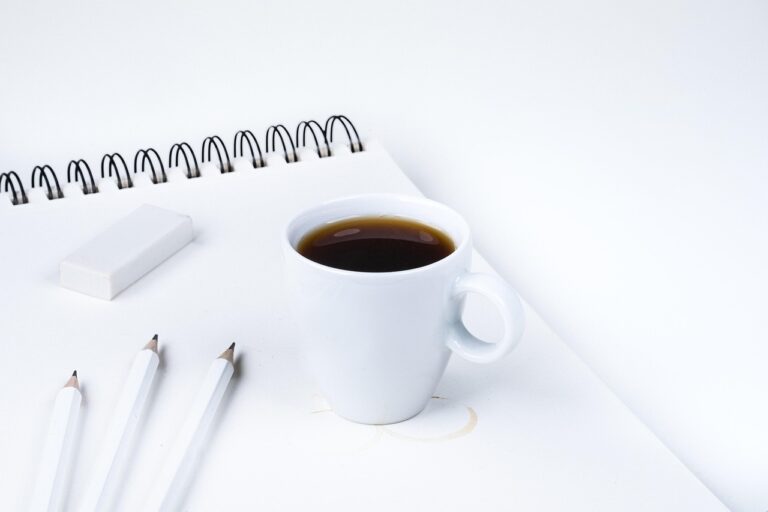人生の終盤に差しかかると、自分が築いた財産を「誰に」「どのように」残すのかを考える場面が増えてきます。
そんなときに重要なのが「遺言書」の存在です。
遺言書があれば、家族間のトラブルを未然に防ぎ、遺された人々に自分の思いを正確に伝えることができます。
しかし、遺言書はただ書けばいいというものではなく、法律上の要件を満たしていなければ無効になる可能性もあります。
ここでは、遺言書の基本から、実際の作成手順、注意点までを詳しく解説します。
遺言書とは何か?
遺言書とは、自分の死後に財産をどう分けるかなどを記した法的文書です。主に以下のような内容を記すことができます。
- 財産の相続に関する希望(誰に何を渡すか)
- 法定相続人以外への遺贈(例:内縁の配偶者、友人など)
- 遺言執行者の指定
- 子の認知
- 特定の相続人を除外する希望(廃除)
自分の意思を明確にし、トラブルを避けるために、元気なうちに準備しておくことが大切です。
遺言書の主な種類
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
- 全文を自分で手書きする方式
- 費用がかからず手軽だが、形式不備で無効になるリスクも
- 2020年から法務局での「保管制度」もスタート(おすすめ)
2. 公正証書遺言
- 公証役場で作成し、公証人が記録
- 法的ミスの心配がなく、最も確実性が高い
- 証人2名が必要で、作成費用も発生
3. 秘密証書遺言(あまり一般的ではない)
- 内容は秘密にできるが、手続きや保管に注意が必要
【ステップ別】遺言書の作成手順
ステップ1:財産と相続関係を整理する
まずは、自分の財産と相続人をリストアップしましょう。
✅ 財産の例:
- 現金・預金
- 株式・投資信託
- 不動産
- 車・宝石・骨董品
- 負債(借金など)
✅ 相続人の例:
- 配偶者、子、孫
- 兄弟姉妹、甥姪
- 法定相続人以外の人物に渡す場合(遺贈)
この段階で、**「誰に何を渡したいのか」**をざっくりとイメージしておきましょう。
ステップ2:遺言内容を決める
「誰に、どの財産を、どの割合で渡すか」を明記します。
以下のような具体的な記載が必要です:
- 長男には自宅(土地・建物)を相続させる
- 長女には金融資産の半分を遺贈する
- Aさんには100万円を遺贈する
- 相続人のうちBさんを遺言執行者に指定する
この段階で、感情に流されず、冷静に全体バランスを見て判断することが大切です。
不公平に思われる内容には、「なぜそのようにしたのか」背景を補足する手紙(付言事項)を添えるのも有効です。
ステップ3:遺言書の形式を決める
✅ 費用をかけずに手軽に済ませたい → 自筆証書遺言
→ ただし、必ず形式要件(全文手書き・日付・署名・押印など)に注意
→ できれば法務局の遺言書保管制度を利用する
✅ 法的に確実な方法を取りたい → 公正証書遺言
→ 公証人が作成、証人2人が必要
→ 家族にトラブルが起きそうな場合や不動産が多い方におすすめ
ステップ4:遺言書を作成・保管する
✅ 自筆証書遺言の保管方法:
- 金庫や貸金庫に保管
- 法務局で保管制度を利用(検認不要でおすすめ)
✅ 公正証書遺言の保管方法:
- 原本は公証役場に保管(自宅にも正本を保管)
🔍 ポイント:作成した遺言書が「見つからない」「破棄された」では意味がないため、信頼できる人に存在を知らせておくことも重要です。
ステップ5:定期的な見直し
- 財産の増減
- 家族関係の変化(離婚、再婚、相続人の死去など)
- 税法や相続制度の変更
これらがあった際には、遺言書の内容を見直す必要があります。
少なくとも3年〜5年に1度は内容を確認しておくと安心です。
よくある失敗例と注意点
❌ 書式ミスで無効になる
→ 日付が抜けている/署名がない/印鑑が不適切
❌ 不公平な配分でトラブルになる
→ 一部の相続人に偏りがある場合は「付言事項」を添える
❌ 財産の記載が曖昧
→ 「○○銀行の預金」ではなく「○○銀行△支店の普通預金(口座番号○○)」と具体的に
まとめ|将来を見据えた賢い準備を
遺言書は、人生の集大成として、自分の意思を家族に伝える大切なメッセージです。
元気な今だからこそ、冷静に将来を見据えた判断ができるもの。
いざという時に「書いておいてよかった」と思えるよう、早めの準備をおすすめします。
専門家(弁護士・司法書士・行政書士・FPなど)に相談することで、自分に合った形で安心の遺言書を作成することができます。
あなたの想いを、大切な人へ正確に届けるために——今からできる「備え」を始めましょう。